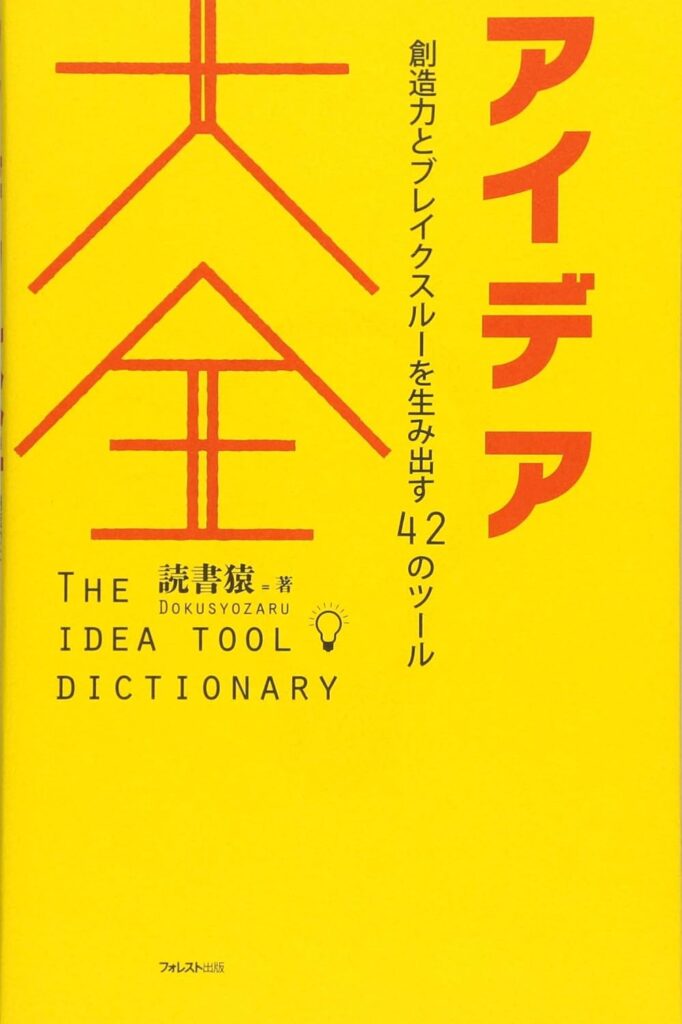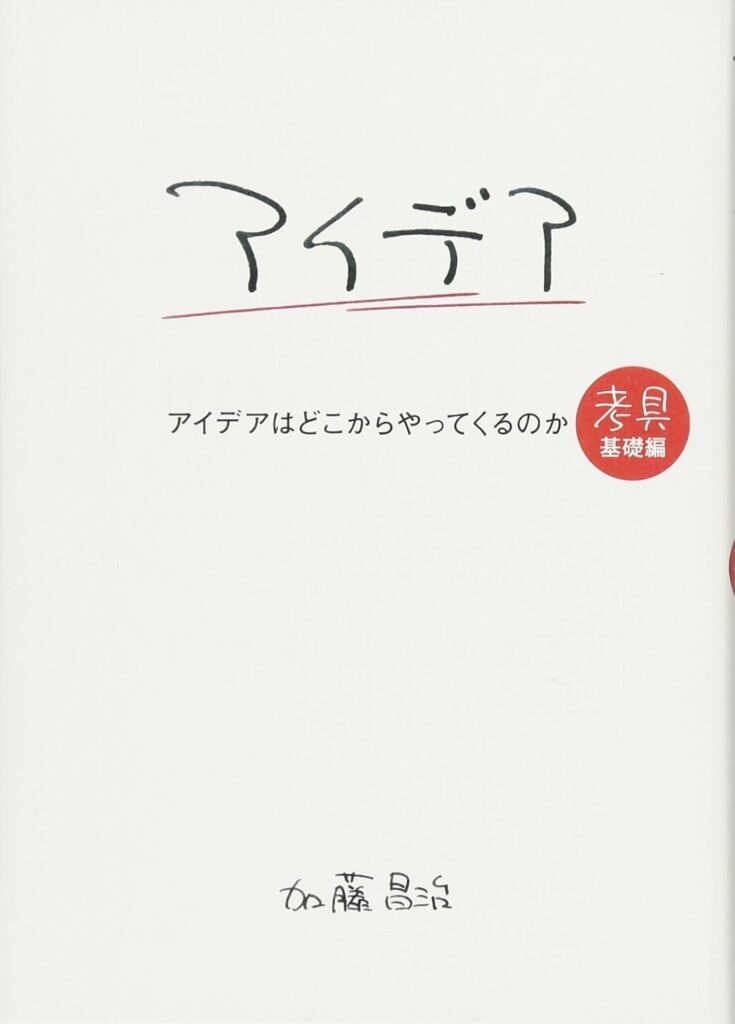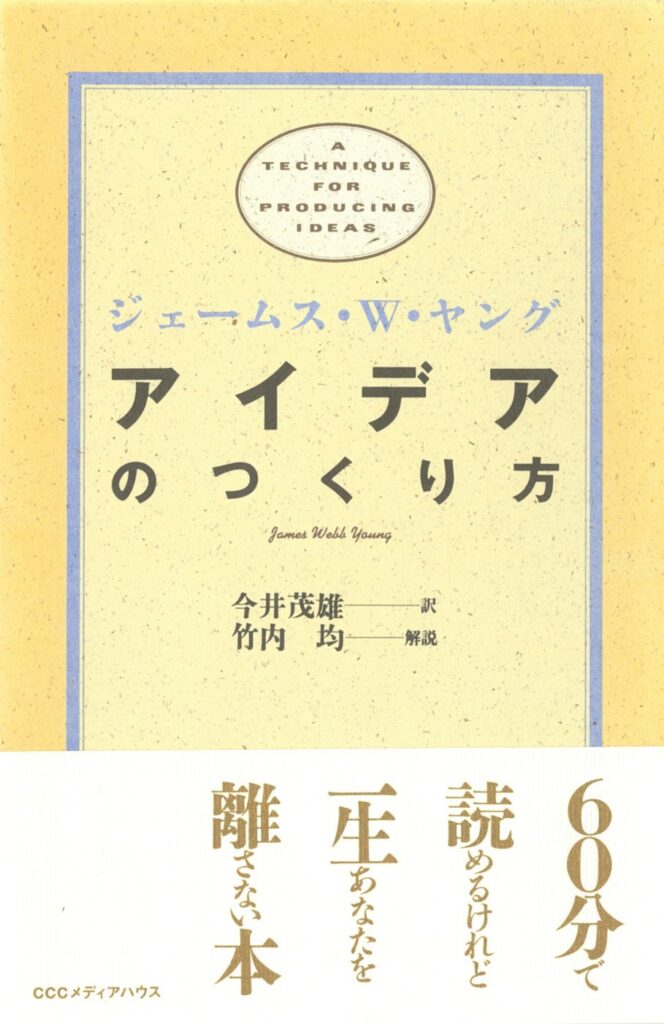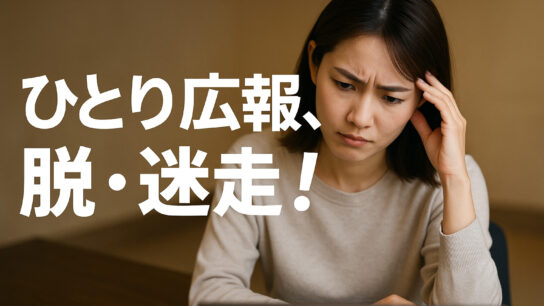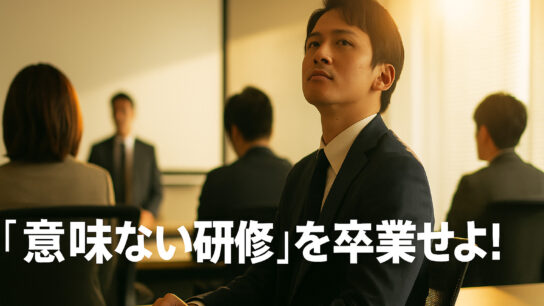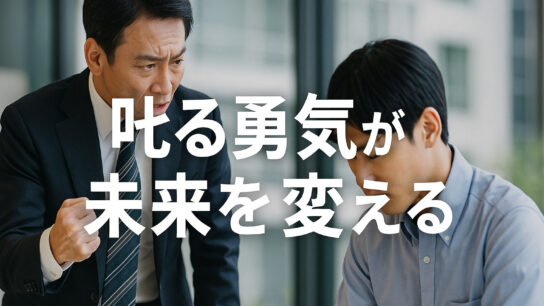企画力は広報の武器
広報担当者にとって、企画力は単なるアイデア出しではありません。それは、戦略と実行力を結びつけ、成果を最大化するための基盤です。
しかし、日々の業務に追われる中で「新しい発想が出てこない」「アイデアが形にならない」と悩む方も多いでしょう。
そこで今回は、最新の企画発想法から、長く愛される定番のフレームワークまで、広報担当者が必ず読んでおきたい3冊を厳選しました。
それぞれの本には、企画を生み出すだけでなく、実行に移すための具体的な方法が詰まっています。読むことで確実に行動が変わり、広報の成果にも直結するはずです。
1冊目:『アイデア大全』読書猿
「アイデアを出すのは苦手ではないけれど、いつも同じパターンになってしまう」という人におすすめなのが本書です。著者・読書猿氏は、古今東西の創造的思考法を80種類以上収集し、実践的に使える形で紹介しています。
特に広報の現場では、「型破り」な発想と「型通り」の発想の両方が必要になります。本書はその両方を強化するためのツール集のような存在で、アイデアが煮詰まったときに参照すれば、新しい視点が必ず得られます。
さらに、本書は単なる理論解説に留まらず、手順や例題が豊富に掲載されているため、自分の案件にすぐ適用可能です。例えばイベント企画のキャッチコピーを考える際や、SNSキャンペーンの仕組みを設計する際にも役立ちます。結果として、日常的にアイデアを量産できる「発想の筋力」がつくでしょう。
2冊目:『アイデアはどこからやってくるのか』加藤昌治
この本は、20年以上にわたり広告・企画の第一線で活躍する著者が、アイデアを形にするためのプロセスを徹底的に解説した実用書です。
特に注目すべきは、「考える前に集める」情報収集法と、「ネタ帳」を使った発想の蓄積術です。広報担当者は日々多様な情報に触れますが、それをどう整理し、どのタイミングで引き出すかが成果を左右します。
本書では、その情報を「企画の種」として活かす方法が明確に示されています。
また、著者が提唱する「視点をズラす」テクニックは、既存の発想を別角度から磨き直すのに有効です。たとえば、単なる商品説明を「ストーリー仕立て」に変えることで、プレスリリースやSNS投稿の反応率を大幅に高めることができます。
企画を思いつくだけでなく、実際に実行まで持っていくためのロードマップとしても最適な一冊です。
3冊目:『アイデアのつくり方』ジェームス・W・ヤング
出版から数十年を経てもなお、多くの企画・広告業界人に読み継がれている名著です。その魅力は、たった数十ページで「アイデア生成の原理」をシンプルに示していることにあります。
ヤングは、アイデアは「既存の要素の新しい組み合わせ」であり、そのためには①情報収集、②熟成、③ひらめき、④検証、⑤実行という5段階を踏むべきだと説きます。この構造は今も全く古びておらず、広報の現場でもそのまま活用可能です。
例えば、取材記事のテーマ決めや、キャンペーンの切り口を探る際、この5ステップを意識すると発想の精度が格段に上がります。また、短時間で読めるため、忙しい広報担当者でも繰り返し読み返して実務に活かせます。
最新の手法と組み合わせることで、この本は「企画力の軸」を支える存在になるでしょう。
まとめ|学んだ企画力を成果に変える
企画力は、一度学べば終わりではなく、日々の実践を通じて鍛え続ける必要があります。
今回紹介した3冊は、それぞれ異なる角度から企画の発想法と実行法を教えてくれるため、組み合わせて読むことで相乗効果を生みます。
広報担当者がこれらを実践すれば、単なるアイデア出しにとどまらず、社内外を動かす力を持つ企画を生み出せるはずです。もし「企画を実務に落とし込むプロセス」に悩んだら、MONWORLDが戦略立案から現場実行まで伴走します。